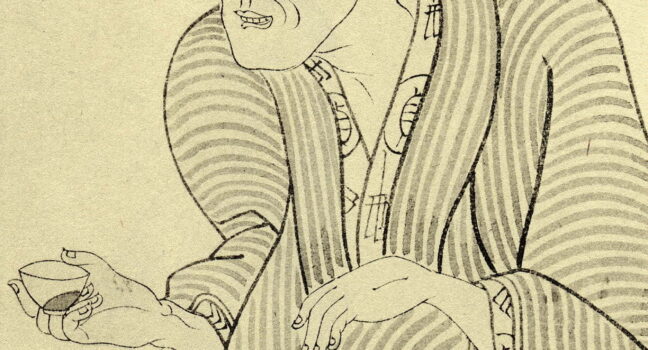どうも、りかちゅうです!「東海道中膝栗毛」という作品は聞いたことありますか?タイトルに道中という言葉がある時点で旅行や旅関係の話かなと。そうですね。旅から生まれる笑い話と思えばいいかと。ちなみに、「東海道中膝栗毛」は江戸の作品で十返舎一九が描いた作品です。日本史に詳しい人や学習したことある人なら聞いたことあるはずです。彼は有名な文化人の一人です。有名だから教科書に載ってるわけですし。ですので、この記事にて彼のことを話しますね!
index
十返舎一九のプロフィール
教科書に載っている人物ではありますが簡単なプロフィールから見ていきましょう!

名前 十返舎一九
生年月日 1765年
没年 1831年
備考
江戸時代最大のベストセラーともいわれる「東海道中膝栗毛」の作者です。ゲラゲラ笑える作品らしいです。そんな作品を書く人だからなのか自分の「死」までもネタにして人を笑わせていたそうです。
十返舎一九の人生
以上が彼のプロフィールです。駿河国出身なのは知りませんでした。まあ、元から名前しか知りませんでしたが。まあ、そんなことはさておき、彼の人生を見ていきますね!
1.生い立ち
十返舎一九は1765年、駿河国駿府で武士の家に生まれたそうです。本名は重田貞一で通称は重田幾五郎です。十返舎一九は1783年の19歳頃に江戸へ奉公に出て、のちに大坂へと移住しました。それから、商人の養子となり同地で創作活動を開始したそうです。
ただ、その当時は十数年ふらふらとした生活を送っていたそうです。とは言っても、ふらふらしながら香道や浄瑠璃などさまざまなことを学んでいたらしいです。具体的には1789年浄瑠璃の「木下蔭狭間合戦」を仲間と共同で作ったことが記録に残っています。
2.重三郎との出会いが転機となる
十返舎一九は1794年頃に再び江戸へ戻りました。この時は30歳頃です。それで、彼は重三郎と出会い運命が変わります。文章も絵も得意だった十返舎一九は重三郎に気に入られ重三郎の元で人気作家の挿絵や用紙の加工などを手伝うようになります。その際に、居候もしていたそうです。
そして、重三郎の薦めで黄表紙などを自作するようになりました。具体例としては1795年に刊行した黄表紙「心学時計草」などでした。それ以降、十返舎一九は江戸で本格的に創作活動へ打ち込むようになります。このように、出版の裏方仕事を続けながら洒落本や滑稽本などさまざまな作品を出し世間に広めていきます。
3.「東海道中膝栗毛」でヒット!
十返舎一九の名が江戸中に広まったのは1802年に刊行された滑稽本「東海道中膝栗毛」の初編が大ヒットしたときです。あまりの好評ぶりから次々と続編が出され1822年の「続膝栗毛 十二編 上中下」まで続きました。約20年も続いた作品だとか。「東海道中膝栗毛」の詳細は別記事にて話しますね!
そして、たびたび取材旅行へ訪れたり当代屈指の人気作家である山東京伝や曲亭馬琴、式亭三馬達と交流を重ね多忙を極めながらも多くの知見を獲得したそうです。ちなみに、十返舎一九はこのような経験をもとに「読本」や「合巻」「人情本」など幅広い分野に進出し毎年20冊程度の作品を刊行し続けました
4.日本初の職人作家?
東海道中膝栗毛が大好評したことで十返舎一九は潤筆料で生計を立てられるようになりました。作家業のみで生活費を稼いだのは十返舎一九が日本初だうです。他の人は何かと掛け持ってたんですね。
ですが、当時の潤筆料はあくまで執筆を約束させるための前金に過ぎません。そのため、金額も決して高くありませんでした。そこで、十返舎一九は膨大な刊行数を手がけ生涯で580以上の作品を発表しました。文章のみならず自分で挿絵を描くことが多く仕事に追われ続けたのです。
5.最期
十返舎一九は多忙だったためだんだんと体調に異常をきたすようになり1810年に眼病を発症。さらに、1822年には中風にかかったそうです。そして、晩年は体の不自由さもあり創作から離れ1831年に67歳で亡くなりました。遺体は「東陽院」に葬られました。
ただ、死ぬ直前でも十返舎一九は笑いをとりました。なんと、葬儀の参列者を驚かせたサービス精神旺盛な逸話があります。十返舎一九は死に際に弟子を呼び「私が死んでも湯洗いして身を清めちゃダメ。絶対に火葬してね!」と伝えました。弟子は遺言の通り亡くなった状態のまま棺桶に入れ火葬すると激しく花火が打ち上がりました。十返舎一九は死装束の頭陀袋のなかに花火をたっぷりと仕込んでいたそうです。そんなことするなんて面白い人ですねwwwww。
十返舎一九の得意なジャンルや作風
このように、死に際まで人を笑わせる十返舎一九はどんなものを得意としていたか?その話もしますね!
1.得意ジャンル
十返舎一九は多様なジャンルの本を作ることができた作家でした。その中でも特に得意としていたのが会話や言動を通して笑いを誘う滑稽本です。十返舎一九は言葉選びはもちろんのこと、登場人物のキャラクター設定に面白味を加えることに長けていました。また、黄表紙「滑稽志つこなし」や合巻「方言修行金草鞋」に代表されるように作品名自体を滑稽に仕立てることも巧みです。要するに、文章や挿絵を創作するだけでなく、自分の作品を魅力的にプロデュースする能力を彼は持っていました。
2.作風
十返舎一九は特定の作風にとらわれず、読者の嗜好や時代の風潮を重視して創作を行いました。そのためら人気作が刊行されるとたびたび脚色を加えて作品化しています。例えば、1804年に刊行した黄表紙「化物太平記」は1797年に武内確斎が出した「絵本太閤記」のパロディです。豊臣秀吉の出世物語として名高い「太閤記」を化物の世界に転化した内容だそうです。
また、世間の流行を敏感に察知し作品に落とし込みました。その代表例が東海道中膝栗毛です。当時の江戸で旅行熱が高まっていたことに着目して創作を開始し、伊勢詣に憧れる人々を読者に取り込もうとしたそうです。十返舎一九は山東京伝や曲亭馬琴に比べて学識が少ない人物でした。そのため、流行を味方に付けることで自身の立ち位置を確立したそうです。
十返舎一九の逸話
晩年まで面白いことをしていた彼には逸話があります。ですので、その逸話についても話しますね!
1.十返舎一九の意味
十返舎一九という名前にはいくつかの意味が隠されています。まず「十返舎」は、「正倉院」に収蔵された手にすると天下人になれるという逸話のある香木「蘭奢待」に由来しているという説が有力です。蘭奢待とは10度炊いても香りが消えないと言われることから「十返しの香」と呼ばれておりここから十返舎の名が作られたと言われています。また、「一九」は本人の幼名「市九」のもじりだそうです。きっと彼は自分の作品は十返しの香さながらに読み継がれることを願ったのかと思われます。
また、異説として昭和時代の小説家松本清張は十返舎一九の「舎」と「一」を読み替えることで意味が浮かび上がると考えました。まず一を「はじめ」と読んで同じ意味の「甫」に置き換えます。そして、舎と「甫」を一字につなげて「舗」を当てると「十返舗九」(気が利かず偏屈な人という意味です)になると松本清張は言っています。真相は定かではないですが筆名に遊び心が息づいている感じがしますね。
2.私生活でも滑稽さを求める
十返舎一九は私生活でも滑稽さを追求し続けたそうです。辞世の句には「此世をば どりやおいとまに せん香とともにつひには 灰左様なら」と書き残しています。これは「そろそろこの世をお暇します。線香の煙と灰のように、最後は、『はい、さようなら』」と言っています。このように、人生の終わりまで言葉遊びをするという振る舞いで周囲を楽しませようとしたのかと思われます。自分の死をエンタメにするなんてそういないですよね。
まとめ
十返舎一九も「東海道中膝栗毛」も教科書に載っている人だなという印象はありました。ですが、それ以上のことはないです。ですが、今回調べてみてこんなに面白いことをする人とは思ってもなかったです。この発見ができたのは「べらぼう」のおかげかと。だからこそ、今後の彼の活躍するところは見どころだなと思っています。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。
りかちゅう