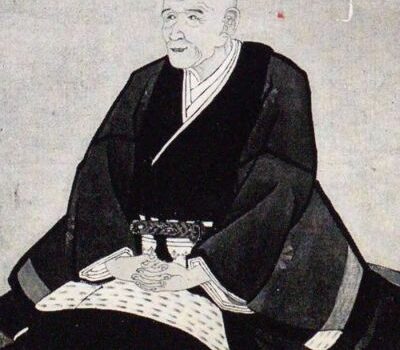どうも、りかちゅうです!重三郎は寛政の改革の時に出版統制令に逆らっていたことから処罰をされてしまいました。ですが、それ以降も重三郎は活動していました。それで、その処罰以降に重三郎がプロデュースしてヒットした人がいます。それは曲亭馬琴です。学校の教科書では滝沢馬琴と書かれている人です。彼は「南総里見八犬伝」で大ヒットしました。なんなら、今の時代でもコンテンツになってます。このように、今の時代にも通ずるものを書いた人です。一体何者なのか?この記事にて話しますね!
index
曲亭馬琴のプロフィール
彼のことは教科者でも載るくらいの有名な人です。ただ、おさらいとして馬琴のプロフィールから見ていきましょう!

名前 曲亭馬琴
本名は滝沢興邦です。
生年月日 1767年7月4日
没年 1848年12月1日
備考
南総里見八犬伝の人です。山東京伝と出会ったことで馬琴は文化人の道を歩みました。それから京伝が重三郎に馬琴を紹介したことで「南総里見八犬伝」という作品が生まれました。
曲亭馬琴なの?滝沢馬琴なの?
曲亭馬琴は滝沢馬琴とも言われています。どっちなんだよと思いますね。これからその話をしますね!
1.どっちも正解!
結論からしたらどっちもOKです。滝沢馬琴は本名の「滝沢興邦」を基にした名前で後の時代に広まった呼び方です。明治以降から滝沢馬琴という言われ方になったそうです。
一方で曲亭馬琴は彼のペンネームで、彼自身が使っていた正式な名前でした。江戸時代では作家がペンネームを使うのが一般的でした。山東京伝や同時代式亭三馬もペンネームで活動していましたからね。
2.曲名馬琴の由来は?
曲亭馬琴という名前にら由来があります。まず、「曲亭」という言葉には江戸時代の文化的な意味が込められています。「曲」とは遊郭を指す言葉で「亭」は書斎や家を表します。要するに、曲亭で「遊郭で生まれた文学」を意味しています。
また、「馬琴」という名前にも意味があります。これは「馬」と「琴」を組み合わせたもので「馬のように力強く、琴のように美しい文学を作る」という願いが込められていたそうです。このように、「曲亭馬琴」という名前には江戸時代の遊び心や文学への情熱が込められていたのです。
曲亭馬琴の人生
以上が曲亭馬琴のプロフィールです!では、彼はどのような人生を歩んだのか?
1.生い立ち
馬琴は1767年に旗本の松平家の家臣滝沢家に生まれました。幼名は倉蔵です。お父さんがのちの俳句をたしなんでいた影響から幼くして「絵草紙」を愛読しわずか8歳で句を詠んだとも言われています。
2.10歳で家督を継ぐ
1775年に馬琴が10歳に父が亡くなると滝沢家が減俸してしまいました。すると、家督を継いだ1番目のお兄さんが不服を訴えて失踪しました。また、2番目のお兄さんは他の家に養子へ出ていたことから家督は馬琴が継ぐことになりました。そのため、10歳なのに七五郎興邦と名乗って松平家で童小姓として働くことになりました。
しかも、仕えた相手は8歳の子どもで大癇癪でありました。その子は周りへのいじめや暴力がそれはひどかったらしいです。そのため、馬琴は14歳の秋についに逃げ出してしまいます。
3.ふらふらした生活
その後は医師を目指したものの、2年ほどして医の修行に挫折しました。それから、一時は1番目のお兄さんの主家へ仕えるもすぐに辞めました。そして、読書仲間のもとへ身を寄せ、好きな読書や写本に明け暮れたそうです。
4.山東京伝との出会い
色々明け暮れている中、京伝に出会いました。京伝は馬琴の6歳年上で浮世絵師としてそれなりに知られていました。ただ、それだけに留まらず戯作者に転向して大成功をおさめます。京伝のことに関してはこちらを見てください!
それで、一介の浪人であった当時24歳の馬琴は京伝にお酒を一樽持って弟子にしてくれと頼みます。ダメ元ではあるものの、深川生まれ深川育ちという共通点を持つ2人はすごく話が弾んだようです。そのため、京伝はこのとき京伝から弟子はとらないが後輩作家として出入りしていいと言ったそうです。
5.重三郎に出会う
京伝は重三郎に馬琴を推薦しました。重三郎は重三郎に力量を認め1792年に使用人として抱えられたのです。このとき、馬琴は武士の身分を捨てるため商家に婿入りして正式に町人となり滝沢瑣吉と名乗りました。
それ以降、馬琴は蔦屋重三郎が営む「耕書堂」で奉公しながら戯作の手ほどきを受け、1796年に読本「高尾船字文」を刊行しました。ここから本格的な執筆活動に入り、読本や黄表紙などの作品を次々と発表していったのです。
6.南総里見八犬伝でヒット!
1802年に馬琴は知見を広げるため京都や大阪周辺への旅に出発しました。その様子を随筆「蓑笠雨談」や「羇旅漫録」にまとめ、新たなジャンルに手を伸ばします。さらに、2600以上の季語を収めた事典「俳諧歳時記」や、長編の読本「椿説弓張月」などを記し、名を上げました。この頃になって馬琴は読本における第一人者に上り詰め、戯作における時代の寵児となっていたのです。
そして、1814年に馬琴は代表作でもある「南総里見八犬伝」の初編を刊行しました。この作品は、庶民を中心に熱狂的な人気を獲得しました。「南総里見八犬伝」の詳細は長くなるので別記事で話せる時に話しますね!
7.最期
それ以降28年にわたって「南総里見八犬伝」の続編を執筆することになりました。途中で馬琴は失明するという困難に見舞われたものの文章を口に出してそれを他者に書き留めてもらう「口述筆記」で創作を続けました。やがて1842年に完結を迎えたのです。それから、晩年も口述した内容を義理の娘が代筆するかたちで創作を継続し、1848年の死の直前まで創作活動を続けました。
葛飾北斎と馬琴
江戸の有名な絵師こと葛飾北斎と馬琴は仲良かったそうです。ですので、その話もしますね!
1.喧嘩するほど仲が良い!
北斎は馬琴の作品にもっとも多く挿絵を描いた浮世絵師でした。そのため、引越しを繰り返したことでも知られる北斎なのに、18006年の春から夏にかけて馬琴の家に北斎が居候したこともあったようです。
ちなみに、この時代の小説の挿絵は作者が下絵を描いて画工がその通りに描くものでした。ですが、馬琴は特に画工への注文が多いし、北斎も自分の絵に対する自信とこだわりが強いためしょっちゅう衝突したそうです。具体例としては馬琴の手紙によると、北斎は絵の中の人物の配置を馬琴の指示に従わず、よく左右の位置を入れ替えて描いたたそうです。そのため、馬琴はわざと左右反対に指示をしておくと思った通りに描いたそうです。
2.まさかの決別?
その後、1804年から1818年の間から2人の合作は見られなくなります。
最後の大喧嘩は登場人物の僧がぞうりを口でくわえる場面を馬琴が指示したことがきっかけだったとか。北斎は
「誰がそんな汚いものを口にくわえるもんか。そんなに言うならあんたがまずくわえてみろ!」と言ったそうです。それに馬琴が激怒したのだとか。この喧嘩がもとでコンビは解消されてしまいました。ただ、北斎の名声が上がり挿絵以外の仕事が忙しくなった説もあります。
まとめ
「富嶽三十六景」の葛飾北斎との繋がりがあったことは知りませんでした。北斎が人の作品の挿絵を描いてるなんて思ってもなかったので。にしても、2人の関係には笑いました。ここまで喧嘩してるのにいい作品が描けるなんてなかなかですよ。でも、喧嘩するほど仲がいいかと思ったら終わっちゃいましたけどね。私も有名な2人の解散は残念には思いました。なんなら、喧嘩した時の作品とか面白いのになとも思いました。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。